Talks vol.2
レコテック株式会社 Circularity Designer 大村拓輝さん
SDGs TALKSは、SDGsに関わる有識者の方をお招きして対談を行うシリーズ企画です。第二回目のゲストは、レコテック株式会社でブランディングを担う大村拓輝さん。 テクノロジーを駆使しながら、廃棄物を資源として循環させることで、ごみという概念のない社会を実現しようとしています。。

ごみを「捨てる」から、「資源として託す」行動に。
高橋 : 今日はお話を聞けることを楽しみにしてきました。まず、レコテックの事業内容を教えていただけますか?
大村さん : レコテックはごみをテクノロジーで資源に変えようというコンセプトを掲げています。
野外音楽イベント「ap bank fes」で大量に出るごみをどう処理すればいいのか環境対策のコンサルティングを行ったり、ごみ問題が深刻なインドネシア・バリ島で生ごみを乾燥させて処理する機械を導入するなど、いろんな形で廃棄物に関わる仕事をしてきました。
高橋 : 最近、自社サービスとして”POOL”をローンチされましたが、これはどういったものなのでしょうか?
大村さん : 資源を循環させるために作ったプラットフォームです。ごみの現状を変えるためには、ごみを資源として使いたい製造業者のための仕組みが必要じゃないかと考えました。
スマホやタブレットを使って情報を連携することで、ごみがどこで、どれだけの量が発生しているかを見える化し、効率よく収集して、最終的にはリサイクル材のPOOL樹脂として提供していく予定です。
“POOL”という名前には、ごみを「捨てる」のではなく、「POOL=次の人に預ける」という行動に変えてほしいと思いが込められています。
高橋 : それは素敵ですね!少しプライベートな話をすると僕は1970年生まれで、高校1年生と小学6年生の息子がいるのですが、彼らはごみを分別するのも当たり前のこととして身に付いているんですよね。
ごみの問題にしてもSDGsにしても、僕はやらなきゃいけないと考えてしまっているところがあって。でも息子たちを見ていると、このペットボトルは繊維になるんだと想像しながら捨てるというのが自然とできる社会もそう遠くないように感じます。
大村さん : はい。まさにこれからの世代が「ごみをPOOLしておこう」と言える社会を目指して、サービスを設計しています。

高橋 : アパレル業界からみて、POOLされた資源は素材に変わるという前提なのでイメージもしやすいですね。最近はさまざまなリサイクル素材も広まってきて一部使用しているのですが、まだコストが高い。消費者が自然と手を出せるようになるためには、価格という問題が必ずつきまといますよね。
大村さん : コストに関しては我々のシステムが大きく寄与できる部分です。というのもリサイクルする過程で一番お金がかかるのは物流コストなんです。
東京・丸の内エリアで行った実証実験の例を挙げると、アパレル店舗から納品時に洋服にかけられているプラスチック製の袋を回収したのですが、1店舗あたり20kgしかなくても、エリア全体で4トンの資源があるとわかれば、4トン車を1台まわせば効率的に回収できてコストを下げられます。しかもアパレルの納品車両を利用して、服を納品した帰りの空きスペースに載せることにしたんです。
高橋 : それはいいアイデアですね。
大村さん : 物流コストだけでなく、従来の燃やしてしまうリサイクルから、素材として再利用するリサイクルに移行したことで、約70%のCO2を削減できたという結果が出ました。今後は東京都全域にプラスチック回収拠点を拡大していく予定です。
ミッションはわかりやすい言葉で伝えること。

高橋 : 大村さんがレコテックに入社されたのはなぜですか?以前はNIKEにお勤めだったとお伺いしましたが。
大村さん : もともと自然がすごく好きで。学生時代に留学していたアメリカのポートランドも人と環境がどう調和するのかを考えて設計された都市でした。ただ、当時は環境問題をビジネスにする考えには至らず、ご縁あって、NIKEに入社して楽しみながら忙しく働いてきたんです。それがコロナ渦をきっかけに、改めて本当にやりたいことはなんだろうと考えるようになって。自然と人間の世界はどうすれば調和するんだろう、そういえば自然の世界にごみという概念はないなと思ったんです。
それでごみという概念をなくしたいと、オランダにあった産業廃棄物を資源にマッチングさせるサービスを日本に持ってこれないかと画策していた時期に弊社代表の野崎に出会って。「同じことを15年前からやっているよ」と言われて意気投合して、入社しました。
高橋 : なるほど、野崎さんが一緒にやろうよと。じゃあ、会社での大村さんのミッションはなんですか?
大村さん : サービスを提供していくうえで、わかりやすく伝えることが僕のミッションだと思います。サービスが複雑化してわかりづらい部分があるので、いかにわかりやすい言葉にしていくか。技術は伝えて、使ってもらえるまでがセットですから。
高橋 : 普及活動ですね。みんないいものは作れるんですよ。でも伝わらないことには売れません。実際私もアメリカとの商品開発のミーティングで中身の良さはわかったから、外側の良さも伝えるべきじゃないかと言われたことがありました。日本人は自己アピールが下手なんですけど、どんな業種でも伝えることって大切ですよね。
製品が寿命を終えた後の責任も考える。ミッションはわかりやすい言葉で伝えること。

高橋 : 今後、レンフロとレコテックが連携できることはあるでしょうか?SDGsに関してもさらに取り組めることがあるのではないかと考えていて。
大村さん : できると思います。SDGsの目標の中で「つくる責任、つかう責任」がメーカーに当てはまると思うのですが、これまで製品を作って納品しておしまいだったのが、今後は製品が寿命を終えたらどうするのか。製造と回収をセットにするのがポイントではないでしょうか。
POOLシステムは回収したいものを効率的に回収するための仕組みなので、靴下を回収する仕組みとセットにしてお客さんに販売できるかなと。
高橋 : それって今後は店舗や企業だけでなく、個人から排出するものも回収していこうというお考えですか?
大村さん : そうです。これから、とある政令指定都市でマンションから排出されるシャンプーボトルや詰替え用パウチ、お菓子のきれいな袋などを回収する実証実験を予定しています。それは誰が回収したいのかというと、製品を作ったメーカー自身なんです。この取り組みは全国に広げていきたいと繊維でもできるのでしょうか?
大村さん : はい。今はプラスチックを回収していますが、マンションに靴下回収ボックスを設置して、適切なタイミングで回収する仕組み自体は難しくありません。ただ、一社単位でやろうとするとうまくいかないので、御社のようにいろんなブランドさんと仕事をしているところが他と連携していけば回収効率を上げられると思います。

高橋 : SDGsの「つくる責任」については、靴下を作る工程で残糸が大量に出るんです。ふわふわの綿状のもので、これまでは廃棄してきました。そこで弊社ではSDGs TALKS VOL.1でご紹介した「おのくん」という靴下を使ったぬいぐるみの中綿として、残糸を使えないかと検討中です。今までもサンプルの靴下を寄贈してきたのですが、もう一歩進んだ取り組みができればと。
大村さん : それはとてもいいですね。
高橋 : 靴下というニッチな産業ですが、いろんな方々との会話からヒントを得て、ひとつずつアクションしていきたい。御社のPOOLを活用した、繊維製品の回収とリサイクルができるタイミングになれば、僕らも使わせていただけるか検討したいです。
自社ブランドHOTSOXは靴下をキャンバスにするというコンセプトで、これまでBanksyといったアーティストとコラボしてきたのですが、次はある団体を通じて、さまざまなハンディキャップのあるアーティストの方々とのコラボレーションを検討しています。もしそれが実現したら、その靴下の素材はサステナブルなものがいいですね。私は関連性のあるもの同士を糸で結び、ビジネスをしていきたいと常に考えています。さまざまなアート靴下とPOOLで生まれた糸を結び、PRもしっかりしていけば結果的に我々のファンになっていただける方も増えるのではと思います。
大村さん : ありがとうございます。今後は繊維をはじめ、あらゆるごみとなっているものに展開していきたいというビジョンがあるので、ぜひ協業できるように取り組んでいきたいです。
製品が作られるプロセスを透明化して伝える。
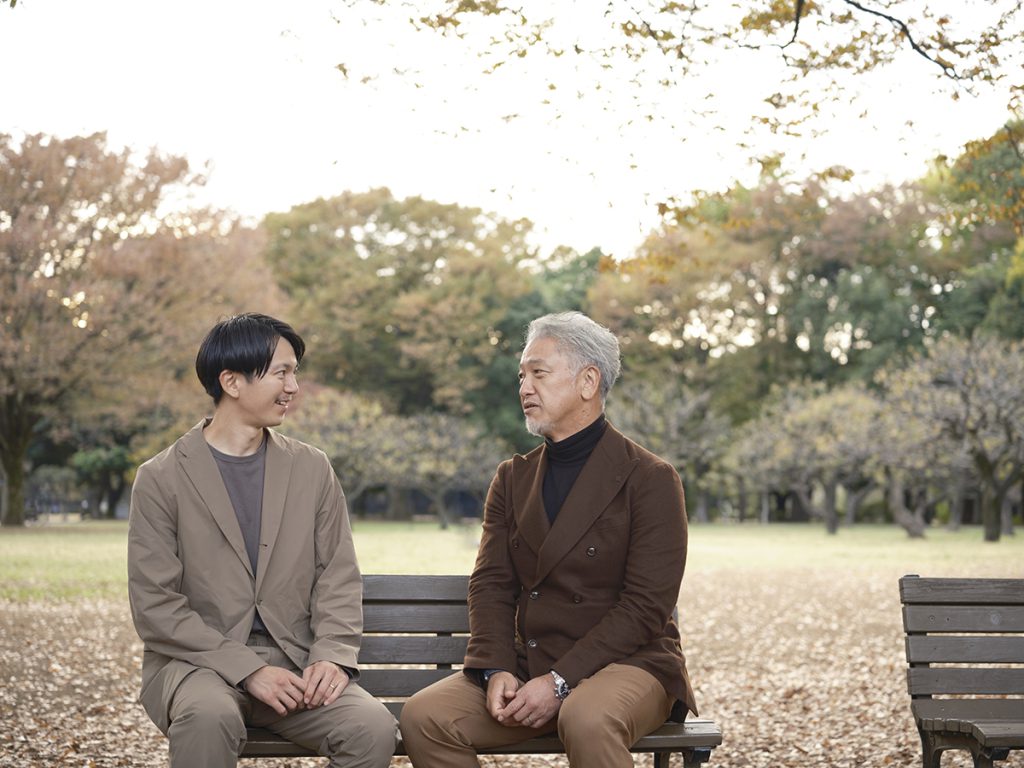
高橋 : 対談を通じてこれからのビジョンも見えてきました。大村さん自身は今後、どのようなメーカーが消費者から選ばれるとお考えですか?
大村さん : 素材を調達したり、作っている過程をどれだけ透明化できるのかが消費者に求められると思います。労働搾取といった問題も浮き彫りになってきて、背景やプロセスを踏まえてお客さんに伝えないと売れなくなる。
高橋 : 農業もそうですよね。生産者の顔が見えるのが当たり前になってきて。ただ、食材だと買う人にとってのベネフィットがわかりやすいのですが、繊維は伝わっていないのが課題かと思っています。原材料の多くを占める綿であれば、綿花がどう育てられているのかも知られていなかったり、オーガニックコットンもまだまだ理解されていません。業界としてもっと伝えていかないといけませんね。
大村さん : そうですね。POOLシステムもどのようなプロセスを経てリサイクルされたのか、トレーサビリティ情報を提供することが肝になっています。これは再生プラスチックですよと言っても、使う人にとっては本当にそうなのかわかりません。そのあたりを透明化していきたいと思っています。

- Editorial Direction : Mo-Green
- Photo : Saori Tao
- Text : Rie Ochi
